構想別カテゴリ
分類別カテゴリ
お問い合わせ
一般財団法人
国づくり人づくり財団
【総本部】
730-0016
広島市中区幟町5-1
広喜ビル4F
地図はこちら
【東日本本部】
100-0014
東京都千代田区
永田町2-9-8-602
地図はこちら
(フリーダイヤル)
0120-229-321
Email info@kunidukuri-hitodukuri.jp
個人情報について
経済づくりコラム
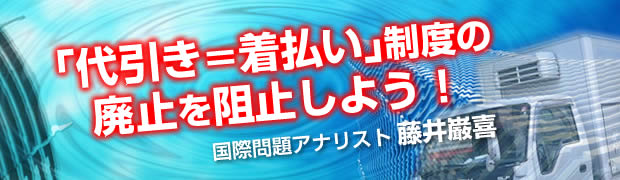
ひどい悪政がまかり通ろうとしている。
宅配便の「代引き=着払い」制度の廃止が強行されようとしているのだ。
 金融庁が後押しして、宅配便(宅急便)の「代引き=着払い」廃止を強行しようとしている。これは、地方経済、中小零細企業のビジネスを弾圧する巨大な政治圧力だ。
金融庁が後押しして、宅配便(宅急便)の「代引き=着払い」廃止を強行しようとしている。これは、地方経済、中小零細企業のビジネスを弾圧する巨大な政治圧力だ。 地方企業、中小企業も、インターネットを利用して、独自の流通を展開できるようになってきた。これを支える仕組みの一つが、「着払い」である。インターネットは必ずしも中小企業の味方ではない。「着払い」を利用できて始めて、インターネットは中小企業の味方になる。 宅急便の「着払い」が禁止されるとどういう事がおこるか?
通販の着払いに依存している地方企業、中小零細企業の売り上げが落ち、倒産が増える。弱小企業切り捨てでもある。離島・山間・僻地の人々が切り捨てられる。まして庶民の金融機関である郵便局の振り替えが、郵便局数の激減で益々使いにくくなっている。僻地には銀行の支店もないから、「着払い」が廃止されると、僻地住人は、「物」が買いにくくなる。 特に持病があり、出歩くことが出来にくいお年寄りにとっては、通販の「着払い」禁止は、暮らしを著しく不便にさせる。
 「着払い」禁止は、ようやく再生の兆しをみせてきた日本の農業をも潰すことになる。有機農業などを実践する良心的農家はインターネット等の通販を通じて、消費者と結びついている。この「生産者=消費者」の直接流通ルートを破壊するのも「着払い」制の廃止である。
「着払い」廃止は、一部の人々には死活問題である。というのもネット通販で買う物の中に「薬」があるからだ。僻地のお年寄りには「死ね」というに等しい悪政である。
「着払い」禁止は、ようやく再生の兆しをみせてきた日本の農業をも潰すことになる。有機農業などを実践する良心的農家はインターネット等の通販を通じて、消費者と結びついている。この「生産者=消費者」の直接流通ルートを破壊するのも「着払い」制の廃止である。
「着払い」廃止は、一部の人々には死活問題である。というのもネット通販で買う物の中に「薬」があるからだ。僻地のお年寄りには「死ね」というに等しい悪政である。薬に関してはもっとひどい事が行われようとしている。09年の6月からインターネット取引による薬の販売がほとんど禁止になる。今売られている品目の67%、(売り上げの90%)のネット販売が厚生労働省の規制により禁止されようとしている。 楽天市場を中心に反対運動が盛り上がり、10万人の反対署名が集められた為、法案は保留となっているが、厚労省は法案立法化をあきらめてはいない。宅急便は、日本人の発明したニュー・ビジネスであり、着払いの機能を合わせ持つ事により、中小零細のビジネス・チャンスを大きく拡げてきた。宅急便・着払いは、日本人独特の相互信頼を生かした素晴らしいシステムである。ヤマト運輸などが、官僚規制と戦いながら創り上げてきた庶民の味方のシステムでもある。
 規制緩和が常に庶民の味方である訳ではない。しかし宅急便は、規制緩和・廃止が新しいビジネスを生み出した典型的な成功事例であり、庶民の生活を大きく活性化した。
ニュー・ビジネスが生み出されただけでなく、宅急便は、崩壊する日本の共同体を支える役割も果たしてきた。都会に住む子供と、田舎に住む親を結びつけ、生産者と消費者を結びつけてきた。「宅急便は町の元気です。」私が何となく思いついたフレーズだが、(似たような言葉がなければ)宅急便業界のキャッチコピーに使かってもらいたい位だ。
規制緩和が常に庶民の味方である訳ではない。しかし宅急便は、規制緩和・廃止が新しいビジネスを生み出した典型的な成功事例であり、庶民の生活を大きく活性化した。
ニュー・ビジネスが生み出されただけでなく、宅急便は、崩壊する日本の共同体を支える役割も果たしてきた。都会に住む子供と、田舎に住む親を結びつけ、生産者と消費者を結びつけてきた。「宅急便は町の元気です。」私が何となく思いついたフレーズだが、(似たような言葉がなければ)宅急便業界のキャッチコピーに使かってもらいたい位だ。宅急便の規制強化は、日本の共同体を更に破壊するのだ。言うまでもないが、この便利なシステムを、日本人は、官からの補助金を一銭ももらうことなしに、否、むしろ官と戦いながら発展させて来たのである。
この宅急便・着払いつぶしは、明らかに官による民の圧迫であり、官僚による規制強化(官僚の利益拡大)である。これは断固粉砕しなければならない。まして日本経済が世界大不況に巻き込まれてゆく中、庶民の自助努力を妨害する官の横暴は、なんとしても許してはならない。
金融庁としては、金融決済機能を、運輸業者が持つ事が残せないのであろう。銀行が決済機能を独占する為に働きかけているのではなく、官僚と戦いながら業績を伸ばしてきた宅急便業界を、官僚が潰そうとしているとしか思えない。
官僚の反撃は猛烈な反撃を受けた金融庁は「宅急便業者が受け取り金をごまかすかもしれないので、消費者保護の観点から必要」などと苦しい言い訳をしている。金融庁は、「着払い」をやる業者には供託金を積ませる、という妥協案を出している。しかしもし供託金制となれば、
1.宅急便の料金は上昇(1000円が2000円に)し
2.中小の宅急便業者は潰れる
という事になるだろう。 2.中小の宅急便業者は潰れる
私の知る限り、この大問題に関して、大マスコミはほとんど報道していない。これも卑怯というしかない。